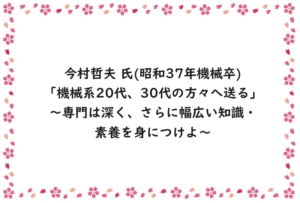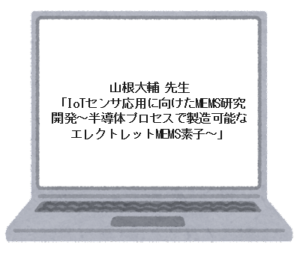鉄の利用:人類の遥かなる営み(4) 【火の利用と文明の進化】
酒井達雄(本学名誉教授/総合科学技術研究機構上席研究員)
前回記事の中で石器時代の生活様式を描いた挿画(図3.2)を示したが、石器で切り裂いた獲物(動物)の肉を火で焼く様子が絵の中央部に描かれています。すなわち、石器時代に人類はすでに火を利用する技術をもっていたことが分かりますが、人類はいつごろから火を利用していたのであろうか?人類が最初に手にした火は、落雷や火山噴火、あるいは風による木々の摩擦熱などによる自然火災によってもたらされたものと考えられています。山火事の鎮火間際に足元に落ちていた木の枝を燃え残りの炎の中に差し出すと、間もなく先端が燃え上がることを人類は知ります。この新たな炎に別の枝の先を近づけるとまた先端が燃え始めます。木の熱伝導率は極めて低いので木の枝の先端が炎を伴って燃えていても多端を持っている手は熱くなりません。このことを知った人類は火を自由に持ち運びできるようになり、火の有効利用が広く普及することとなります。また、人類は山火事で焼かれた動物の肉を食べると美味しく衛生的(殺菌作用)なことをすでに知っており、上記の方法で野火を居住地まで移動させ、獲物(動物)を焼いて食べるような生活様式が徐々に確立されていきます。また、このような便利な火を絶やさず継続的に有効利用するために、複数の居住地や複数の集落で木の幹や枝を断続的に炎の中に投げ入れて、宝物の火を持続的に守るような生活習慣が定着することになります。人類学に関する文献によれば、人類と他の動物の基本的な違いは、火の利用と言語の使用と記載されています。人間の野営地で夜中に火を焚くことが、野獣から身を守る効果的な方法ですが、火を制御できる人間と火に恐怖のみを抱く他の動物との根本的な違いが、その根底にあることが興味深く思われます。
1929年に発掘された中国の周口店遺跡では50万年前の北京原人が火を使っていた痕跡が発見されていますので、人類は50万年以前に火を利用する技術を確立していたことになります。ここで、自然火災による火の利用から、人工的に火を起こす発火技術による火の利用に進歩した時期について、筆者は幅広く文献を調べましたが明確に記載されている文献は見当たりません。しかし、いくつかの文献を総合的に繋ぎ合わせると自然発火による野火を利用し始めたのは170万年~20万年前のようですが、説により大きなばらつきがあります。また、人工的な発火技術についても、40万年~12万年前に東アフリカ、中近東、ヨーロッパの各地域で独自の発火方式が開発されたようです。その内で多くの地域で広く定着したいくつかの発火方式を紹介します。最初に火溝式とよばれる発火方法を紹介しましょう。これは割り竹や硬い木の棒の先端を比較的柔らかい丸太や木の板に強く押し当て、溝を掘るように同じ場所を前後に繰返し激しく擦る方法です。この発火技術は現在でも太平洋のいくつかの島々で実用されており、図4.1はオーストラリアから東1700km辺りに位置する太平洋上の島国バヌアツ共和国で実際に行われている火溝式発火方法の写真です。次に、木と木を激しく擦り合わせて摩擦熱を利用する別の方式として図4.2(a)に示すキリモミ式の発火技術があります。さらに、同図(b)に示すような硬い火打石を互いに打ち付けて火花を造り、乾燥した芝やキノコなどを火種にして燃え易い枯葉や小枝などを燃やす発火法があり、日本でも江戸時代後期までこのような発火方法が実用されていました。

人類は、このように石器時代から近現代に至るまで人工的な発火技術により「火」を得て、食物を調理したり、寒冷地や寒冷期には暖をとり、危険な野獣から身を守るなど、実に幅広い領域で「火」を利用した便利な日常生活を体現してきました。このような太古からの火の利用を通じて、もう一つ特筆すべき点は、炭の発見とその有効利用です。自然発生した山火事などで、その燃え跡に不完全燃焼した黒っぽい燃えカスが残っており、このような燃えカスを再度燃やすと新しい木を燃やしたときより、はるかによく燃えて、高温が得られることを発見します。ご存知のとおり、木は多くの炭素と水分を含んでおり、大量の木を積み上げて燃やしたり、太い木を燃やすと表面付近では炭素と空気中の酸素が反応してよく燃えますが、表面から遠い深部では高温に晒されることで水分だけ蒸発して炭素が残ることになります。こうして、もとの木より熱量の大きい炭ができることになります。山火事などの際に、土を被った状態の木が燃えた場合も完全燃焼ができず、水分だけが抜けた炭素の塊りとして「木炭」ができることを知りました。これらの経験をもとに、人類は土で窯を造り、その中に大量の木材を詰めて蓋をして、少量の空気を供給しながら焚火で中を高温に加熱し、効率的に木炭を作る技術を確立します。すなわち、「木」に比べて「木炭」により「火」の加熱温度を高くする技術が開発された訳です。
以上は、石器時代に始まった「火」の利用と「木炭」の発見・発明の経緯ですが、この木炭の利用は次に続く人類史を大きく左右することになります。大量の木炭を造れるようになった結果、鉱物資源を高温に加熱することができるようになり、スズを含んだ銅鉱石を溶融できるようになりました。純銅の融点は1083℃ですが、適度のスズを混ぜると融点が800℃程度まで低下します。ここで、機友会会員の皆さんは本学理工学部機械系学科の卒業生であり、とくに機械工学科の卒業生の多くは在学中に「工業材料」、「金属材料」などの科目を履修された筈です。これらの科目の中で一度は鉄-炭素系の「平衡状態図」を学んだ筈です。そうです。縦軸に温度をとり、横軸に炭素含有量(%)をとったややこしい図です。細かいことは横に置くこととしますが、この平衡状態図を参照すると、純鉄(炭素含有量0%)の融点は1538℃ですが、炭素を4.3%程度混ぜると融点は1148℃まで低下します。教科書やノートが残っている場合は、一度ご確認いただくと本記事の趣旨がよくご理解頂けると思います。すなわち、銅であっても鉄であっても、他の元素を混ぜると融点がかなり低下することは金属学の基礎知識です。石器時代にこの基礎が体系化されていたとは思えませんが、人類は銅にスズを適度に混ぜると融点が低下することと、純銅に比較してスズを混ぜた方が著しく強くなることを既に理解していたことを、多くの遺跡や文献が示唆しています。
このような背景の中で、人類は今から6000年ほど前より銅鉱石を加熱して溶融する技術の開発に挑戦しており、5000年~4000年前になるとエジプトやメソポタミア、キシュ(現在のトルコ付近)やクレタ島などの地域で銅とスズの合金である「青銅」の製造技術が確立・発展したようです。さらに3000年~2000年前になると中国の四川省成都市北部の三星堆で大規模な青銅器製造が行われたようであり、三星堆遺跡や同博物館には大量の発掘品が保管・展示されています。幸いにも2007年に四川大学で開催された超高サイクル疲労に関するシンポジウムの折に、筆者はPlenary Lectureをさせて頂くことになり、当地を訪問させて頂く機会を得ました。その折に上記の三星堆遺跡を見学し、遺跡の規模の大きさと出土品の豊富さ、さらに技術レベルの高さに驚きました。

図4.3は遺跡見学時に撮影した出土品の写真であり、同図(a)は高さ44.5cm、口径41.8cmの青銅製容器で、3頭の牛と6羽の鳥を配置した装飾が施されています。この青銅容器は酒や水を入れる容器であり、文献によれば日常生活で使用されるものではなく、主として祭祀用の神器として用いられたようです。同図(b)は青銅製面具(仮面)であり、この遺跡には多種多用の面具が多く出土しています。下側の写真の仮面は高65cm×幅139cmのサイズですが、突出した瞳の部分は直径9cm×長さ16.5cmです。目が異様に飛び出ていることは、古代人が目に生命が宿ると思考した象徴と考えられているようです。また、同図(c)は世界最古の青銅製の神樹です。殷代晩期のもので、全体の高さは396cmで、この神樹には3段から枝が出ており、各段に3本の枝が出ています。各枝の中程に鳥が飾られており、全部で9鳥が見えるとともに、各枝の先端には果実が拵えてあります。このような巨大で複雑形状の神樹を青銅で造るのは容易でありません。文献によれば、エジプト、メソポタミア、キシュ、クレタなどの遺跡で発掘された青銅器は、高温で叩いて成形された鍛造品が多かったようですが、三星堆遺跡の青銅器は高温で溶融された青銅を鋳型に流し込んで成形する鋳造品が主体となっているとのことで、三星堆における鋳造技術のレベルの高さが窺えます。なお、図4.3(c)の写真を注意深く観察すると、複雑な形状の部分をいくつかに分割して鋳造し、それらを繋ぎ合わせていることが分かります。
今回の記事では、石器時代に人類が「火」の利用を初めたことを起点として、徐々に「火」の利用技術が向上し、高温の加熱が可能になり、今から5000年ほど前から青銅を広く利用する青銅器時代に推移すしたプロセスを簡潔に纏めてみました。地球上の色々な地域で、それぞれの時代にそこに住む先人達が創意工夫を凝らし、試行錯誤を繰り返しながら、便利で快適な生活を実現するために、弛みなく努力を重ねてきた遥かなる人類の営みに、改めて敬意を払う次第です。